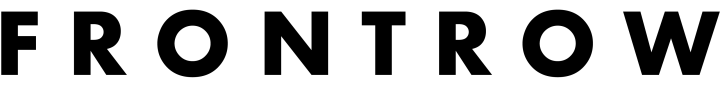LGBTQ+を食い物にする「クィアベイティング」とは?


昨今、海外で改めて問題視されている「クィアベイティング(Queerbaiting)」とは? (フロントロウ編集部)
LGBTQ+の注目度や話題性を搾取する「クィアベイティング」
LGBQT+にまつわる話題が連日世間で注目を浴びるなか、「極めて卑怯なやり方」と批判を浴びているマーケティング手法がある。
それが、ゲイだけでなく、レズビアンやバイセクシャル、トランスジェンダー、クロスドレッサー(自身の性を表現するにあたり、異性装を行う人)なども包括する概念である「クィア(queer)」という言葉と、釣りなどに使うエサを意味する「ベイト(bait)」という言葉を組み合わせた「Queerbaiting(クィアベイティング)」。

実際には同性愛者ではないのに、ある人物やキャラクターが、あたかも同性愛者であるかのように匂わせたり、わざとバイセクシャルを予感させるような表現を使うなどして“性的指向の曖昧さ”をほのめかすことで、LGBTQ+の視聴者や消費者をはじめ、世間の注目を集めようとするこの商業戦略は、エンターテインメントや音楽、ファッションといったポップカルチャーの分野で昔から横行してきた。
「クィアベイティング」の起源
「クィアベイティング」という言葉が誕生したのは、2010年代初頭。映画・メディア研究の専門家である米アリゾナ州立大学のジュリア・ヒンバーグ教授は、当時大ブレイクしていた米CWのドラマ『スーパーナチュラル』や英BBCの『SHERLOCK(シャーロック)』といった作品の中で同性の登場人物たちが、まるでお互いに友情や師弟関係以上の感情を抱いているかのような表現が登場したことが「クィアベイティング」という言葉が生まれるきっかけとなったと英BBCに解説。

ジェンセン・アクレス演じるディーン(右)とジャレッド・パダレッキ演じるサム(左)のウィンチェスター兄弟がアメリカ合衆国各地を旅しつつ、超自然的存在(悪霊、悪魔、怪物など)を狩っていく米CWの人気アクション・ホラー・サスペンスドラマ『スーパーナチュラル』。

ベネディクト・カンバーバッチ(右)が名探偵シャーロック・ホームズ役を演じマーティン・フリーマンが助手のワトソン役を演じた英BBCの大ヒット作『SHERLOCK(シャーロック)』
いたずらに同性同士のロマンスについて期待を抱かせておきながら、結果的には納得のいく展開にならなかったことで、LGBTQ+コミュニティや作品ファンたちから「視聴者を誤解させる」、「ミスリードだ」といったクレームが勃発。“クィアを釣る行為”という意味を持つ「クィアベイティング」という言葉が使われるようになった。
製作者側は、保守的な視聴者や顧客を刺激しすぎず、かつ、LGBTQ+を含む幅広い層にアピールできる便利な戦略として長年クィアベイティングを使ってきた。しかし、LGBTQ+に対する理解が深まり、権利運動が盛んになった昨今では、LGBTQ+を食い物にするようなこのマーケティング戦略は、社会全体にとって「有害である」と厳しい目が向けられるようになっている。
有名ブランドのキャンペーンが炎上
クィアベイティングの例として最も記憶に新しいのが、人気モデルのベラ・ハディッドと “バーチャル・インフルエンサー”のリル・ミケーラが登場した米ブランド、カルバン・クライン(Calvin Klein)のキャンペーン「I Speak Truth in #MyCalvins(アイ・スピーク・マイ・トゥルース・イン・マイ・カルバン)」。
カルバン・クラインの公式SNSで公開されたベラとリル・ミケーラの熱烈なキスシーンをフィーチャーした動画は、CGで作成された架空の女性であるリル・ミケーラとトップモデルのベラが、性別の壁や人間とバーチャル・キャラクターの壁を越え、現実と非現実の境界線を曖昧にした表現が幻想的だと話題に。
しかし、LGBTQ+コミュニティからは「明らかなクイアベイティングである」として批判が殺到した。
ベラは実生活では異性である男性ミュージシャンのザ・ウィークエンドと数年にわたって交際している異性愛者であり、そんな彼女がレズビアンを連想させる女性同士のキスを含むキャンペーン動画に起用されたことに「なぜわざわざストレートの女性を起用するのか」、「なぜ同性愛者を登場させなかったのか」と難色を示す人が続出。

ベラ・ハディッドと恋人のザ・ウィークエンド。
カルバン・クラインがLGBTQ+の顧客を獲得するためや、先鋭的でクールなブランド・イメージを創り上げるために、あえて異性愛者であるベラを起用してクィアベイティングを行なったとの指摘が相次いだ。
炎上を受け、カルバン・クライン側は、この動画は指摘されているような意図で制作したものではないと弁解したものの、「異性愛者を同性同士のキスシーンに起用することは、クィアベイティングだと認識される行為だと理解しています」と過ちを認め、公式に謝罪した。
LGBTQ+の注目度や話題性をマーケティングツールとして使うこの行為が問題視される一方で、一部では、人々がクィアベイティングに厳しく目を光らせるようになったことこそが、社会の流れが前進している証だとポジティブにとらえる人もいる。
まずは、「一体、クィアベイティングの何がいけないのか? 」、「どういった行為がクィアベイティングと見なされるのか? 」を議論し、深く理解すること、そして、不正は糾弾していくことが、これまでLGBTQ+のアイデンティティーを翻弄し、LGBTQ+カルチャーを都合よく商品化してきた“作り手”や“売り手”の姿勢を正すことに繋がるのかもしれない。(フロントロウ編集部)