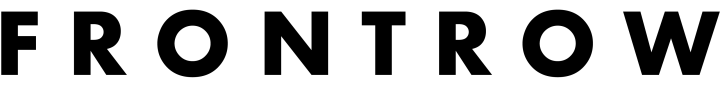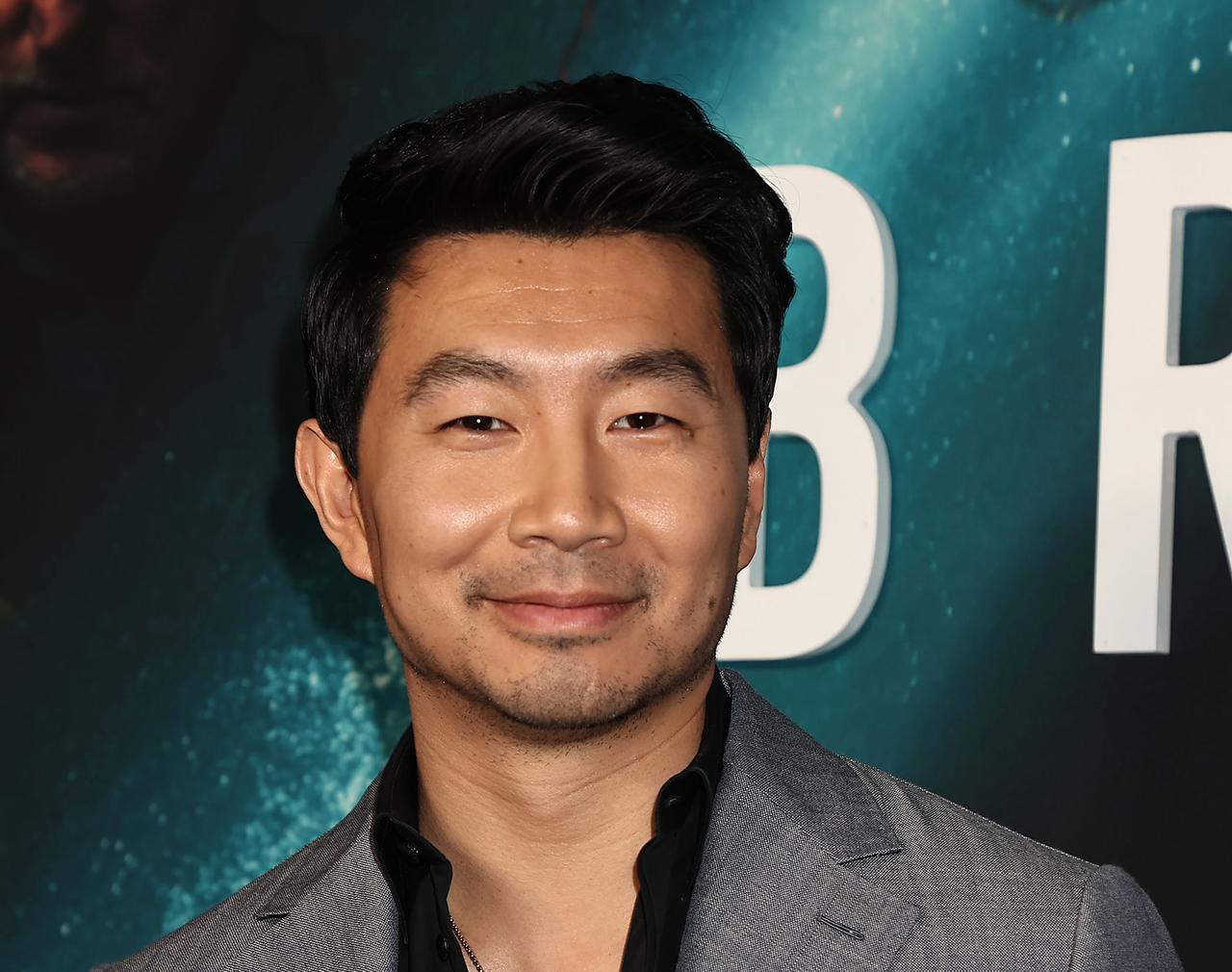フェミニストとして有名なモデルのエミリー・ラタコウスキーが、自分さえも女性軽視の価値観に影響されたことがあると語った。(フロントロウ編集部)
エミラタ、自分のイメージを“利用”している
“神ボディ”の異名を持ち、モデルや俳優として活躍するエミリー・ラタコウスキーは、フェミニストとしても多くのアクションを起こしてきたことで有名。政治とも深い関わりのあるフェミニズムだけに、エミリーのように甘いマスクを持つ女性たちが、政治的発言はできない/しないほうが良いと言われてきたことに、たびたび声を上げている。

そんなエミリーは現在、エッセイを書いていると英GQに明かす。「モデルとしての経験を書きたいと思ってる。自分のイメージを利用した人、そして多分、自分のイメージの犠牲になった人として」。そう言って、自身のイメージが、“神ボディ”で“イケてる女の子”というようなものであることで、様々な経験を乗り越えてきたことを匂わせたエミリー。彼女にとって、モデルという職業はアートなものではないという。
「私にとっては、自分のイメージを使って、モデルとして活動して、それを利用しているのは、生き残るため。私自身を表現するものというよりも」
エミリー・ラタコウスキー、自分の中の差別意識を自覚
エミラタの愛称でも知られる彼女といえば、その内面はフェミニズムや政治など社会問題に関心の高い女性。自分の腕に「くたばれ、ハーヴェイ(※1)」と書きポーズをキメたり、セミヌードで中絶禁止法(※2)に反対の意を表したり、モデルとしてボディやルックスに注目が集まることを逆手に取って意見を発信する上級テクを取っている彼女だけれど、幼少期の頃を振り返った際には、「私にはこの体以上の価値があることを世界に教えて欲しかった」と話したこともある。
※1:ハリウッドでMeToo運動が起こるきっかけとなった、大御所プロデューサーのハーヴェイ・ワインスタインのこと。
※2:2019年に、アメリカのアラバマ州で可決された中絶禁止法。この法律では、近親相姦やレイプなどの性的暴行の被害によって妊娠した場合でも中絶できない。また賛成した25人の議員は、すべて男性であることで、女性の身体に関する法律を男性が決めるなという批判が多く上がった。

腕に「Fuck Harvey(くたばれ、ハーヴェイ)」と書いてカメラの前に登場したエミリー・ラタコウスキー。
そんなエミリーは、2019年に発売された俳優デミ・ムーアによる自叙伝『Inside Out(原題)』を読んで、自分の中にも女性軽視の価値観があったと告白した。
「最近では、声を上げる人も多くなってきた。自分たちの中にある女性に対するイメージが、どれだけ根深いものかってことだよね。私だって、その価値観のなかに落ちたことがあるんだから。(中略)デミ・ムーアについて、偏った推測を持っていたことに気がついたの。女性俳優としての彼女に対して、多少なりとも決めつけがあった。彼女はセクシーで、あの体型だから。私はエミラタなのによ。これってすごく皮肉的でしょ。どれだけ(女性自身の)内面にも根深く女性軽視があるかってことだよね」
自身が経験してきた女性差別に声をあげ、若手セレブ界を代表するフェミニストの一人として知られるエミリー。しかし、女性の多様性を体現する彼女でさえ、育ったこの世界の価値観に影響されるのは避けられない。自分には差別意識はない、ではなく、まずは自分のなかにある差別意識を自覚して、それをなくしていくことが重要。
自分を演じてしまう女性は多い
エミリーと同じように、女性である自分自身が女性を軽んじる価値観や行動に陥っていたと明かしている女性はほかにもいる。マーベル映画『ブラック・ウィドウ』やNetflix映画『マリッジ・ストーリー』などで知られる俳優のスカーレット・ヨハンソンは、2018年に行なわれたウィメンズ・マーチで、全世界の女性に向けてこうメッセージを贈っている。

「私は、気がねなく一緒に過ごせる“めんどくさくない女の子”だという物語を作り出さなくてはいけませんでした。それは、時には自分が正しいと思うことを妥協しなくてはいけないということでした。そして(当時は)自分自身にもそれが大丈夫なことに思えていました。相手が意図的だったかどうかは別として、自分の意見を妥協し、自分自身を見えなくし、劣っている者としていたんです。女性が習慣として必要としてしまっている、承認を得るために。
これは、自分のクリエイティブな価値や、プロとしての価値、そして性的な価値が、ただひとつ、男性からの承認や欲求によってだけ決まるという、非常に多くの若い女性たちも経験している感情によるものです。たとえ私が、自分自身に敬意を払うことが1番重要だという会話がされるような家庭出身だったとしても、女性でいるということだけで、私には不利なのです。なぜなら何世紀もの間、女性は礼儀正しく、感謝し、男性に合わせなくてはいけないと教えられてきたのですから。
最近、自分の人生に新しい言葉を取り入れたので、ここにいる方々と是非シェアしたいです。『もう媚びない』。自分に正しいことが起こっていないと感じる時に、それが他人の感情を傷つけるからといって罪悪感を感じるのは止めましょう」
(フロントロウ編集部)