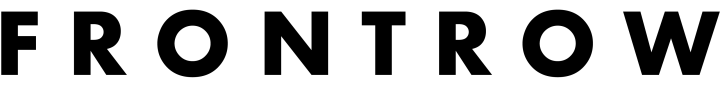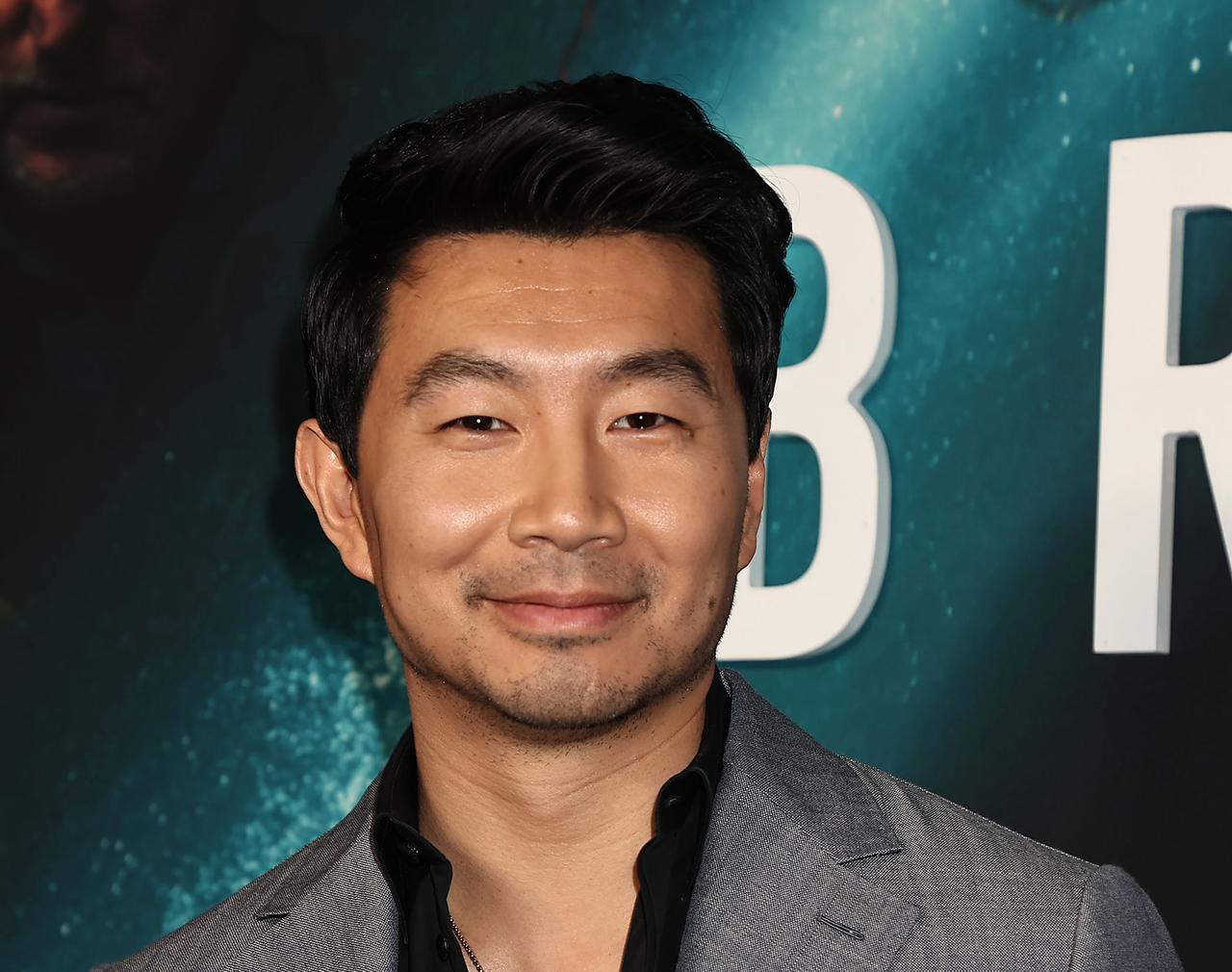実際に起こった性暴力事件に着想を得ている映画『ウーマン・トーキング 私たちの選択』だが、じつはユーモアが多い。その理由について、監督やキャストが思いを語った。(フロントロウ編集部)
シリアスななかでユーモアがある『ウーマン・トーキング 私たちの選択』
2009年にボリビアで、キリスト教の教派メノナイトの女性100名以上が数年にわたりレイプされていたことが発覚した。その事件に着想を得たミリアム・トウズによる小説『Women Talking(原題)』を、『アウェイ・フロム・ハー君を想う』のサラ・ポーリー監督が映画化。非常に高い評価を得ている。
本作は、宗教コミュニティという閉ざされた環境のなかで、女性たちが直面した性暴力や女性軽視を描き、タイトルが「話す女性たち(Women Talking)」であることが示すとおり、会話から女性たちが覚醒していく姿を追う。キャラクターたちの間で展開される会話が重要となる本作についてポーリー監督は、民主主義とは何なのかというテーマも含んでいると、米EWで話している。
テーマがシリアスであり、衣装やセットもカラフルではないことから、作品が非常に暗い印象を受けるが、じつは本作にはユーモアも少なくない。その効果について、俳優のケイト・ハレットは米Colliderのインタビューでこう分析した。

「本作のような映画では軽いシーンもあることによって、暗いシーンがより感情に訴えかけ、よりインパクトのあるものになるため、本当に重要だと思っています。とくにこの映画では、サラが会ったメノナイトの女性たちは、あの部屋でユーモアと笑いがあることは重要だと、非常に明確にしました。メノナイトの女性たちは男性がいない時に集まると、たくさん笑い、おたがいに触れ合うことも多かったそうです。サラはその事実に光を当てたかったし、本当に素晴らしい仕事をしたと思います」
本作が含むユーモアが、メノナイトの女性たちが直々に要望していたことだというのは驚き。さらに、女性たちから意見をもらった監督自身も「自分の人生の悲劇で、コメディとともに起こらなかったことはないように感じます(笑)」と、米EWのインタビューで話しており、共感したよう。そして彼女は、人間として生きることについての考えを語っている。

サラ・ポーリー監督
「のちのち面白い話にならないトラウマな経験をしたことは、私はありません。なので、どこの場面でも笑う機会がなく、とてもクレイジーで、悲しく、そして難しい映画を買うことはないです。私にとっては、それ(笑いをともなう悲劇)が人間であるという経験です」
何かしらの被害者、とくに女性の性暴力被害者に対しては被害者非難が起こることが多く、そのなかには被害者が笑顔を見せた時に、“被害者のくせに笑顔になれるのか”といったようなものがある。
しかし、生きていかなければならないのに、つねに苦しく悲しい気分のままでいなければいけないわけがない。また、笑顔になれるからといって、心の別の部分にある苦しみや悲しみが消えわけでもない。それが、「人間である」ということだろう。
監督が、メノナイトの女性たちが、どうやってユーモアを楽しんできたのか。女性への暴力を描く本作だからこそ、その点にも注目したい。
(フロントロウ編集部)